最新の研究助成公募案内(締め切りました)
奨励研究・若手研究・助産実践研究助成金の一般公募について
2026(令和8)年度 研究助成公募を締め切りました。
【受付期間】 2025年8月25日(月)10時~11月14日(金) 30日(日)
一部締切延長しました。
延長対象:奨励研究助成B、若手研究助成、助産実践研究助成
(奨励研究助成Aは14日(金)をもって受付を締め切らせていただきます)
※締切をもって自動クローズしますのでご注意ください。
一部締切延長しました。
延長対象:奨励研究助成B、若手研究助成、助産実践研究助成
(奨励研究助成Aは14日(金)をもって受付を締め切らせていただきます)
※締切をもって自動クローズしますのでご注意ください。
【公募概要】
公募案内、実施要項、研究助成金の使途に関する注意事項を確認の上、期間内に申請フォームより申請ください。
| 奨励研究助成公募 | ||
| 奨励研究助成公募案内 | 奨励研究助成実施要項 | 申請はこちらから |
| 若手研究助成公募 | ||
| 若手研究助成公募案内 | 若手研究助成実施要項 | 申請はこちらから |
| 助産実践研究助成公募 | ||
| 助産実践研究助成公募案内 | 助産実践研究助成実施要項 | 申請はこちらから |
| ※研究助成金の使途に関する注意事項 | ||
※申請内容登録後の修正はできませんので、登録完了前に入力内容に誤りはないか、十分ご確認ください。
※研究代表者は当該研究組織を代表し、その中心となって研究のとりまとめを行い、助成金の管理及び報告事務を含めて、研究の計画・遂行に責任をもちうるものとします。また、同一研究者(研究代表者)に対しての助成は累計3回までとします。
【選考方法】
日本助産学会理事会にて審議決定し、採択結果は申請者へ電子メールで通知いたします。採否理由については公表いたしません。
過去の研究助成採用者一覧
研究報告書の一部については、表題をクリックするとPDF文書で閲覧できます。
| 年度応募総数 | 委託研究 / 表題 | 奨励研究 / 表題 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 1)奨励研究助成A:1件 2)奨励研究助成B:3件 3)若手研究:7件 |
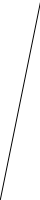 |
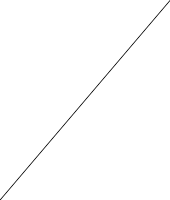 |
A 富田 綾 |
硬膜外麻酔分娩直後の母体の内因性オキシトシン濃度の変化:分娩時の薬剤投与量や早期母子接触との関連 |
| B 鷲尾 弘枝 |
助産師が行うウイズコロナ時代の妊産婦口腔内環境の評価 | |||
| B 岡山 智子 |
男性不妊の精液の質改善を目的としたセルフケアの解明 | |||
| B 増澤 祐子 |
妊産婦や子育て中の女性の地域における支援ニーズの探索:患者・市民参画の枠組みを用いた調査 | |||
| 若手 神徳 備子 |
妊娠初期~末期の女性とパートナーにおける不眠症およびメンタルヘルスの実態調査 | |||
| 若手 豊本 莉恵 |
「エビデンスに基づく助産ガイドライン 2024」刊行に向けた妊娠期CQのシステマティックレビュー | |||
| 若手 櫻井 佐知子 |
タンザニアにおける妊娠高血圧・子癇予防行動を育むインフォグラフィック教材による参加型プログラム:準実験研究 | |||
| 2022 1)奨励研究助成A:2件 2)奨励研究助成B:5件 3)若手研究:6件 |
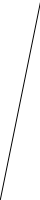 |
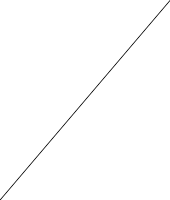 |
A 長田 知恵子 |
搾乳技術習得のためのシステム構築に向けた調査 ー経験年数による搾乳技術の相違ー |
| B 相川 祐里 |
周産期メンタルヘルスケアにおける支援者支援-スーパービジョンシステムの開発- | |||
| B 大田 えりか |
バングラデシュの妊産婦死亡率低減に向けた効果的な介入に対する予測モデリング研究 | |||
| B 増田 恵美 |
ICTを活用した妊婦の腰痛改善を目的としたヨガストレッチプログラムの実行可能性 | |||
| 若手 丸山 菜穂子 |
周産期Domestic Violence被害者支援導入の実装 | |||
| 若手 中井 抄子 |
助産師のマタニティヘルス・ケア能力の評価尺度の開発と妥当性の検証 | |||
| 若手 松原 愛海 |
ハイリスク新生児におけるデバイス固定による皮膚損傷の発生要因探索 | |||
| 2021 1)奨励研究助成A:4件 2)奨励研究助成B:6件 3)若手研究:4件 |
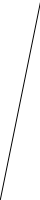 |
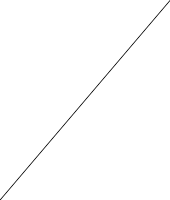 |
A 吉田 美香子 |
産褥早期の尿閉回復過程と関連要因の検討:縦断観察研究 |
| B 笹川 恵美 |
新生児の授乳行動への麻酔分娩等の医療介入と早期母子接触による影響:前向き観察研究 | |||
| B 江藤 宏美 |
レストレスレッグス症候群とビタミンD欠乏症との関連 | |||
| B 藤本 久江 |
LFD(light for date)児出生予防につながる妊娠中の食習慣に焦点を当てた行動変容プログラムの開発 | |||
| 若手 瀧本 千紗 |
夫婦関係が周産期ボンディングに与える影響:前向きコホート研究 | |||
| 若手 山田 安希子 |
産後早期における育児・日常生活行動の支障感が女性の心理的健康に与える影響 | |||
| 若手 竹下 舞 |
助産ケアの質指標を用いた医療改善プログラムの実装評価:混合研究法 | |||
| 若手 松永 真由美 |
妊娠糖尿病妊婦に対する多職種連携・継続支援のためのクリニカルパス導入に向けた医療者向け教育プログラムの開発と評価 | |||
| 2020 1)委託研究助成:1件 2)奨励研究助成A:2件 3)奨励研究助成B:5件 4)若手研究助成:9件 |
村上明美 | 産科医療補償制度の補償対象において助産所がかかわった事例の分析 | A 白石三恵 |
妊娠前、妊娠中のボディイメージによる妊娠中の食事摂取・身体活動への影響:前向きコホート研究 |
| B 松井弘美 |
助産師現任教育における分娩期の異常の臨床判断力を育成する Script Concordance Test の開発 | |||
| B 小澤千恵 |
アドバンス助産師を対象とした産後の母親への心理支援の質向上 | |||
| B 中野美穂 |
未受診で出産に至った母親の子どもの養育に関する意思決定支援の実態調査 | |||
| 若手 岡津愛子 |
周産期うつ・不安のハイリスク妊婦に対する認知行動療法的介入プログラムの開発と評価 | |||
| 若手 本田沙織 |
過去5年間の伊豆諸島在住妊婦における妊娠および出産の現状 ~合計特殊出生率高値の要因探索~ | |||
| 若手 山本真実 |
分娩期における新人助産師の臨床判断能力の強化に向けた実地指導者への教育プログラム | |||
| 若手 米澤かおり |
分娩時の食事摂取と出産アウトカム、産婦の疲労感、出産満足度との関連 | |||
| 若手 伊藤絵美 |
乳児への揺さぶり行動を予防するためのVR学習教材の開発 | |||
| 2019 1)奨励研究助成A:2件 2)奨励研究助成B:6件 3)若手研究助成:5件 |
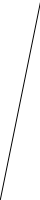 |
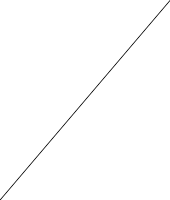 |
A 橋本麻由美 |
デルファイ法を用いたラオスの看護学生の分析的思考実践能力アセスメントツールの開発 |
| A 中田かおり |
生殖世代の男性を対象とした妊娠前の情報提供プログラム試案の開発 | |||
| B 松崎政代 |
産後1か月の母親のスマートフォン過剰使用と母子の情緒的結びつき(ボンデイング)との関連 | |||
| B 野口真貴子 |
助産師教育に携わる教員の労働生産性と健康に関する研究 | |||
| B 横手直美 |
なぜ麻酔分娩から自然分娩へ回帰するのか~フランスの助産師の助産ケアに対する認識の変容とその影響要因~ | |||
| B 野原留美 |
シミュレーション動画を用いた分娩期の助産トレーニングプログラムの開発 | |||
| 若手 笹川恵美 |
就労妊婦のマイナートラブルに関する要因探索と労働生産性へ及ぼす影響の実態把握 | |||
| 若手 宍戸恵理 |
妊婦の妊娠後期から産褥早期の唾液オキシトシン値の変化と産後疲労感とマタニティブルーズとの関連 | |||
| 若手 新田祥子 |
Informatin and Communication Technology(ICT)を活用した分娩場所意思決定支援ツールの開発 | |||
| 2018 (H30) 1)奨励研究助成A:5件(うち1件は取り下げ) 2)奨励研究助成B:7件 3)若手研究助成:2件 |
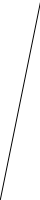 |
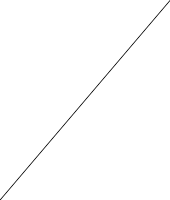 |
A 春名めぐみ |
助産師外来・院内助産ケアと妊娠・出産アウトカムとの関連:大規模観察研究 |
| B 北園真希 |
胎児に異常が見つかった女性を支えるケアの開発と評価-バース&ペアレンティング・プランニング- | |||
| B 大田えりか |
セミオープンシステムを利用した妊婦による母子アウトカムへの影響に関する後方視的縦断研究 -継続的な助産ケアを受診した妊婦と比較して- | |||
| B 相川祐里 |
臨床助産師を対象とした周産期メンタルヘルスケア研修の立案・実地・評価 | |||
| 若手 米澤かおり |
育児支援の場面で活用できる新生児皮膚トラブルアセスメント尺度の開発と信頼性・妥当性検証 | |||
| 若手 森田千穂 |
育児期夫婦のコミュニケーション・スタイルと育児に対する役割分担観およびその満足度の関連 | |||
| 2017 (H29) 1)奨励研究助成A:6件 2)奨励研究助成B:5件 |
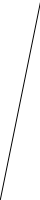 |
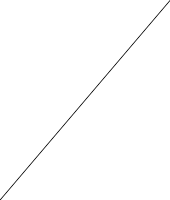 |
A 竹形みずき |
ベトナム都市部で増加する帝王切開の実態と背景因子-母親や医療者の出産や医療に対する思いに関する質的調査- |
| B 園田 希 |
赤ちゃんとふれ合う体験「Mama Touchプログラム」とオキシトシンの関連 | |||
| B 麓 杏奈 |
助産師の心的外傷体験に対するストレスマネジメントプログラムの開発 | |||
| B 菊地 栄 |
福島県原子力発電所事故後の福島県在住母子の健康への影響の検討と未来に向けた母子ケアへの指針研究 | |||
| 2016 (H28) 7件 (7) |
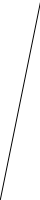 |
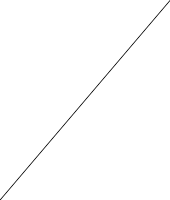 |
中澤貴代 | 助産師学生が行うバースレビューの内容と教育的関わりに関する検討 ~デルファイ法を用いて |
| 東原亜希子 | 骨盤位に対する妊婦のセルフケアによる灸の効果 -ランダム化比較試験 実行可能性の検討(Feasibility Study)- | |||
| 篠原枝里子 | 正期産で出生した母乳栄養児における臍帯結紮のタイミングの乳児早期の貧血予防に対する効果:ランダム化比較試験 | |||
| 2015 (H27) 10件 (10) |
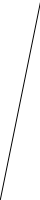 |
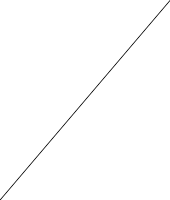 |
藤田愛 | 助産教育におけるSNS型eポートフォリオの活用と助産実践能力習熟度および卒業時到達度の評価 |
| 増澤祐子 | 分娩後出血の予防介入と子宮収縮活動の関連性 -外側陣痛トランスジューサを用いて- | |||
| 乾つぶら | 山間部居住の妊婦において産科施設までの距離が分娩時の入院と分娩体験に与える影響 | |||
| 2014 (H26) 11件 (11) |
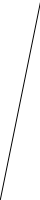 |
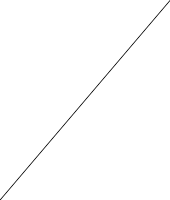 |
桃井雅子 | 不妊治療後の妊産褥婦に関わる看護師・助産師のための教育プログラムの評価 |
| 堀田久美 | 助産師による産後女性への超音波診断装置を用いた骨盤底筋群機能回復支援の検討 | |||
| 白石三恵 | 妊婦の野菜摂取に関する要因の検討‐効果的な野菜摂取促進プログラムの開発をめざして‐ | |||
| 2013 (H25) 6件 (6) |
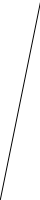 |
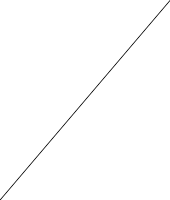 |
蛭田明子 | 分娩後出血シュミュレーショントレーニングプログラムの評価:助産師を対象としたパイロットスタディ |
| 早瀬麻子 | マタニティヨガの介入が妊婦の睡眠覚醒リズムおよびストレスに及ぼす影響 | |||
| 朝澤恭子 | 不妊治療中のカップルに対するパートナーシップ支援プログラムの効果 | |||
| 2012 (H24) 11件 (5/6) |
片岡弥恵子 | e-learningによる分娩後出血対応に関する助産師継続教育プログラムの評価 | 子安恵子 | 褥婦における本態性肩こりの実態調査と緩和プログラムの有効性の検討 |
| 杉本敬子 | 出産による心的外傷後ストレス症状と産後うつ症状の関係における社会的支援の役割 | 谷口初美 | 分娩介助レベルに応じた状況設定シミュレーション教育プログラムの開発 -助産診断・技術の強化と学生の主体性そしてFDの生活化のために- | |
| 2011 (H23) 5件 (4/1) |
春名めぐみ他 | 分娩恐怖感(Fear of Labor)の尺度開発とストレスホルモンや分娩アウトカムとの関連性の検討 | 該当者なし | |
| 2010 (H22) 7件 (3/4) |
堀田久美 | 分娩期の肛門括約筋損傷の実態と損傷要因の検証 | 中村幸代 | 妊婦の冷え性がもたらす分娩時のアウトカム評価 |
| 鈴木美和 | 大学病院におけるハイリスク妊婦を対象とした助産師外来の検討 | 長田知恵子 | 医療介入の時期判断が必要な授乳期の乳腺炎のための鑑別診断ツールの開発 | |
| 2009 (H21) 7件 (1/6) |
江藤宏美 | EBMに基づく助産ケアのガイドラインの開発と評価 | 小黒道子 | ミャンマー・国境出稼ぎ労働者によるHIV/AIDSが母子保健に及ぼす影響と生活実態 |
| 関塚真美 | 妊婦の健康維持を目指したストレス評価指標の有用性の検討 | |||
| 千葉陽子 | 助産学・周産期ケアの学術論文で用いられる英語の分析-英語論文の理解や執筆のために- | |||
| 2008 (H20) 8件 (3/5) |
春名めぐみ | 分娩進行の評価指標としての唾液中プロスタグランヂィンの簡易的な測定方法の開発 | 新川治子 | 妊娠中のマイナートラブルと睡眠に関する研究 |
| 山岸由紀子 | 施設内における助産ケアの検討~産後の母子ケアを中心に~ | 松永佳子 | 産褥1ヶ月までのサービスシステム構築に関する研究 | |
| 2007 (H19) 6件 (2/4) |
松崎政代 | 妊産の日常生活身体活動とそれに及ぼす影響要因に関する研究-妊婦身体活動質問紙と運動に関する地域環境調査の日本語版開発- | 粟野雅代 | 母乳育児の自立支援プログラムの開発と効果 |
| 赤井由紀子 | 妊産褥婦にとってQOLの高い出産とは-高出生率県の“Care in normal birth :a practical guide”の検討-に関する研究 | 日高陵好 | 硬膜外麻酔出産を選択した初産婦の出産体験知に関する研究(日米比較調査) | |
| 2006 (H18) 9件 (2/7) |
小笹由香 | 着床前診断に対する女性の認識とそれらを取り巻く社会の現状 | 安達久美子 | 10代妊婦の支援のあり方に関する研究 |
| 江藤宏美 | 助産所の出産に関する情報集積システムの構築 | 立岡由美子 | 近年の自然分娩の分娩所要時間の再考と新しい分娩予測指標の作成 | |
| 2005 (H17) 13件 (2/11) |
塚本浩子 | ケトン体と体組織を用いた妊婦の栄養・体重管理指針の検討 | 小川久貴子 | 10代妊婦の周産期における支援に関する研究-10代妊婦の中間づくりを通して- |
| 桃井雅子 | 助産実践能力の比較-学部4年次教育課程と大学院修士課程において- | |||
| 2004 (H16) 16件 (1/15) |
松崎政代 | 安全な妊娠・出産のための妊婦の日常生活習慣評価に関する研究-評価指標としての酸化ストレスマーカーの有用性について- | 加納尚美 | 子どもが母親の出産に立ち会うことの心理的影響に関する研究 |
| 藤村一美 | 病院助産師の職業性ストレスおよびケアの質と労働・職場環境との関連 | |||
| 鈴木和代 | 出産直後カンガールーケアにおける母児の安全なポジションの検討 | |||
| 2003 (H15) 10件 (4/6) |
村上明美 | 妊産婦支援における産科医師と助産誌のコラボレーション | 福島裕子 | 多胎児を持つ母親と家族への看護支援-妊娠期からのピアサポートの試み- |
| 長岡由紀子 | -妊娠・出産の安全性と快適さを追求した病院の取り組み- | 宮里邦子 | 足浴による分娩促進作用-自律神経に対する足浴の作用機序に関する基礎的研究- | |
| 2002 (H14) 2件 (1/1) |
該当者なし | 片岡弥恵子 | ドメスティック・バイオレンス被害者の支援ガイドラインの開発 | |
| 2001 (H13) 13件 (5/8) |
江藤宏美 | 医療事故防止のための開業助産婦のケア指針 | 柳吉桂子 | 妊娠期における助産ケアモデルの開発 |
| 藤本栄子 | 出産に関わる継続したケアシステムの消費者と提供者への効果 | 月僧厚子 | 上子を家族立ち会い出産に参加させた母親の体験に関する研究-出産から3年後の追跡- | |
| 2000 (H12) 25件 (5/20) |
村上明美 | 日本の助産婦が持つべき実践能力と責任範囲に関するの産婦の認識 | 宮崎文子 | 損益分岐点分析を用いた助産院経営モデルの検討-全国有床助産院の調査から- |
| 村上睦子 | 助産婦が行なうモニタリングケア及びサポーティブケアの構造化と助産婦の臨床能力の明文化の試み | 葉久真理 | 産褥期の乳腺変化と乳汁分泌との関係に関する研究 | |
過去に採択された研究助成
これまでの応募件数と採用件数は表1のとおりである。いずれも、選考委員会において、研究内容として「日本助産学会が助成するにふさわしい研究」、「社会的・学術的要請度の高い研究」、「独創的・先駆的な研究」であること、応募者の能力としては「研究遂行能力」、そして「経費の合理性」を基準に選出された 研究課題である。
表2は選出された研究課題を便宜上、大きな枠組みとして領域別に分類したものである。研究内容は、助産ケア、指標の開発、実践能力、業務管理、経営など多岐にわたっている。これらの研究結果の詳細は、2年ごとの報告書を参考いただきたい。
こうした助産に関する研究の地道な集積が、我々自身の将来の専門性につながっていくと考えている。
| 年度 | 応募件数(261件) | 採択件数(108件) | ||
|---|---|---|---|---|
| 委託(40) | 奨励・若手(221) | 委託(21) | 奨励・若手(87) | |
| 2000 | 5 | 20 | 2 | 2 |
| 2001 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 2005 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 2006 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2007 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2008 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2009 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2010 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2013 | 6 | 3 | ||
| 2014 | 11 | 3 | ||
| 2015 | 10 | 3 | ||
| 2016 | 7 | 3 | ||
| 2017 | A6/B5 | A1/B3 | ||
| 2018 | A5/B7 若手2 |
A1/B3 若手2 |
||
| 2019 | A2/B6 若手5 |
A2/B4 若手3 |
||
| 2020 | 1 | A2/B5 若手9 |
1 | A1/B3 若手5 |
| 2021 | A4/B6 若手4 |
A1/B4 若手4 |
||
| 2022 | A2/B5 若手6 |
A1/B3 若手3 |
||
| 2023 | A1/B3 若手7 |
A1/B3 若手3 |
||
| 領域 | 委託(21件) | 奨励・若手(87件) |
|---|---|---|
| 妊娠 | 3 | 17 |
| 分娩 | 6 | 14 |
| 産褥 | 2 | 13 |
| 新生児/乳幼児 | 0 | 6 |
| ウィメンズヘルス | 1 | 10 |
| 管理 | 8 | 13 |
| 教育 | 1 | 14 |
